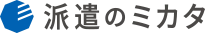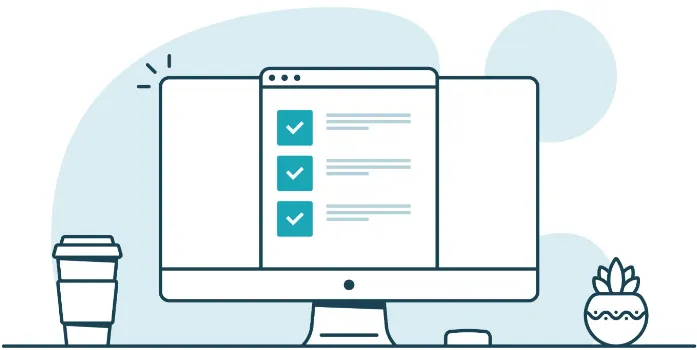ブログ/コラム
派遣法 2022年01月12日
同一労働同一賃金に罰則はある?リスクの回避方法を紹介

派遣のミカタで派遣社員への労務もよくわかる!
派遣法にそったキャリアアップ教育訓練が対応可能!
5,600以上のレッスンが見放題!
利用企業1,600社以上 / 継続率99%
14日間無料トライアルできます。トライアル終了後、安心の請求なし!
同一労働同一賃金を守らなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。 今回は万が一、同一労働同一賃金に違反したらどうなるのかを解説していきます。
目次
そもそも同一労働同一賃金は何を目指している?
同一労働同一賃金では、雇用形態の違いによらず、同じ仕事をしている人は同じ待遇のもとで働けるようにすることを目指しています。
労働者はどの雇用形態を選んでも、能力や仕事ぶりに応じた賃金や福利厚生を受けられるようになります。
昨今は労働の多様化と改善を求めて、働き方改革が政府主導で行われており、今回もその一環となります。
厚生労働省が示している「同一労働同一賃金ガイドライン」では、同一労働同一賃金についての具体的な考え方や例が紹介されております。
同一労働同一賃金を守らなくても罰則はない
厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン」を公表していますが、これはあくまでも基本的な考え方を示すものであり、法的拘束力はありません。ただし、同一労働同一賃金に関わらず、雇用形態以外の待遇について個別に罰則が設けられている場合もあるので要注意です。例えば、男女の違いを理由に賃金に差をつけた場合、国籍、信条で差をつけた場合などがこれにあたります。
同一労働同一賃金に違反すると損害賠償請求を受ける可能性がある
同一労働同一賃金の適用後に雇用形態の違いによる不合理な格差があった場合、企業に対して説明が求められることもあります。よって企業が明確な説明をできないと、損害賠償を請求される可能性もあります。
過去にも、不合理な格差を理由として最高裁が損害賠償を認める判決を出しており、その内容とは「非正規雇用で退職金がない不平等さ」に対しての訴えでした。
原則として、正社員とその他を比較して、差別的な賃金を設定することは厳禁。正社員との配置の違いや業務の違いで差が出るのは許容範囲ですが、正社員が楽な仕事で、その他が過酷な仕事に就かせるといった、不合理と判断できる配置転換も厳禁となります。また、賃金は会社への貢献度に対して支払うものなので、過酷な労働で会社に貢献しているのであれば、当然正社員やその他の配置よりも賃金は高くなければならないのです。
派遣のミカタで派遣社員への労務もよくわかる!
派遣法にそったキャリアアップ教育訓練が対応可能!
5,600以上のレッスンが見放題!
利用企業1,600社以上 / 継続率99%
14日間無料トライアルできます。トライアル終了後、安心の請求なし!
同一労働同一賃金違反によるリスクを避けるには?
違反によるリスクを避けるためには、あらかじめ対策が必要となります。以下の例を参考に対策を講じましょう。
- 雇用形態によって待遇に差が出る場合は、合理的な理由をきちんと説明できるように準備すること。
- 雇用形態に関わらず仕事ぶりや成果を正しく評価できる体制を整えること。
- 政府の支援制度や民間企業が提供するサービスを活用して、同一労働同一賃金に対応した労働環境を整備すること。
- 給与明細の賃金項目に、正社員しか含まれない項目がある場合は、差がないように調整する事。また差がある場合は説明をすること。
- 派遣労働の場合、派遣先への給与確認などを事前に行う事。また派遣先の場合は事前に派遣元に通知すること。
- 就業規則の改善も必要になること。
同一労働同一賃金に対する準備を整えて無用なリスクを避けよう
同一労働同一賃金に違反しても罰則はないが、損害賠償などのリスクが発生する可能性があります。十分な準備を整えて危険を避けられる行動を選択しましょう。
派遣のミカタで派遣社員への労務もよくわかる!
派遣法にそったキャリアアップ教育訓練が対応可能!
5,600以上のレッスンが見放題!
利用企業1,600社以上 / 継続率99%
14日間無料トライアルできます。トライアル終了後、安心の請求なし!
派遣法対応に役立つおすすめサービス
1,300社以上の導入実績を持つ「派遣のミカタ eラーニング」は、派遣法改正により義務化された派遣スタッフのキャリアアップ教育を丸ごと効率化する、派遣業界特化のeラーニングサービスです。
様々な業種に対応する約20種類の教育カリキュラムと、3,000を超える多様な学習コンテンツが搭載されているので、eラーニング導入時に負担となる、カリキュラムの作成や教材の制作なども必要ありません。
受講者と学習データの管理、事業報告用の実績算出もラクラクなので、難しい操作や設定もなく簡単にeラーニングを導入・運用することができます。
また、派遣法改正やトレンドに合わせてほぼ毎月コンテンツを更新しているため、在職期間の長い従業員の教育や派遣社員以外の社員教育にもご活用いただけます。キャリアアップ教育に必要な機能がすべて揃って、月額費用はわずか19,800円〜!
派遣のミカタで派遣社員への労務もよくわかる!
派遣法にそったキャリアアップ教育訓練が対応可能!
5,600以上のレッスンが見放題!
利用企業1,600社以上 / 継続率99%
14日間無料トライアルできます。トライアル終了後、安心の請求なし!
こちらの記事もおすすめ
教育 2022年01月13日
人材派遣の教育訓練はどう進める?
目次派遣法改正の意図とはキャリア形成を支援する教育が鍵教育訓練の導入ステップを解説キャリアアップ支援におすすめのeラーニングサービス 派遣法改正の意図とは 派遣法改正は2015年9月30日に施行されま...
派遣法 2022年01月13日
派遣の義務教育化!教育訓練の方法3つのメリットデメリット
目次【集合研修】相互啓発できるが日程調整がむずかしい!【OJT】実践的だが体型的な指導は難しい!【eラーニング】時間や場所を選ばないがネットワーク環境が必要!教育手段は組み合わせるのが効果的!派遣事業...
派遣業界情報 2023年10月25日
人材派遣の受け入れで役立つキャリアアップ助成金とは?メリットやコースなどを解説
人材派遣を利用する際に助成金を受給できるのはご存知ですか?派遣社員を受け入れて正社員に転換した場合、あるいは待遇を整備したうえで派遣社員を受け入れる場合、「キャリアアップ助成金」の活用が可能です。 こ...